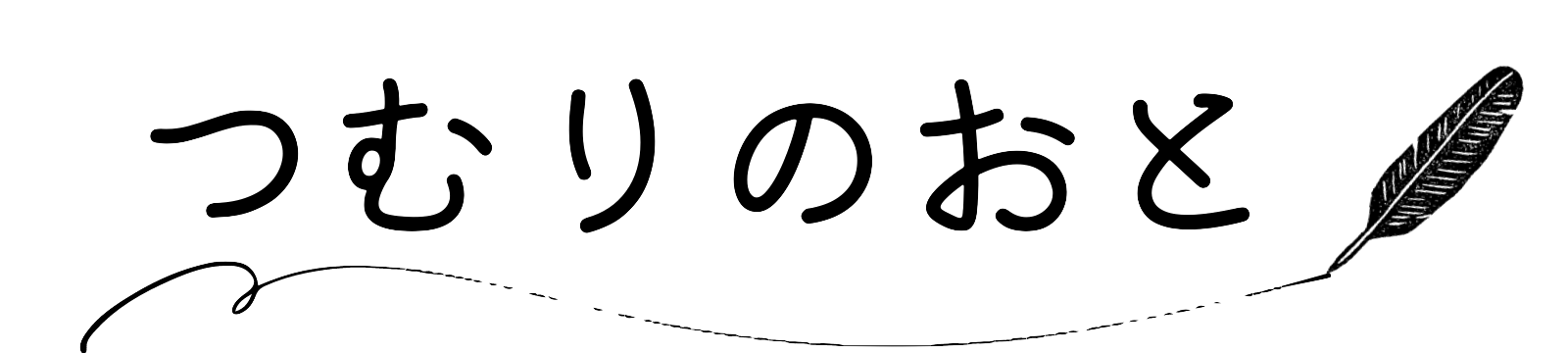こんにちは。つむりです。
娘が生後半年の頃から2歳を過ぎた現在まで、1日30分間の「語りかけ育児」を実践しています。
これはイギリスの言語治療士サリー・ウォードさんが開発した育児法で、元々は言葉に遅れや障害を持つ子どものために開発した方法を、0歳代の乳児に応用したものです。
言語発達が遅れ気味の10ヶ月児に介入して7歳頃まで追跡した調査では、対照群に比較して知能指数が高く、集中力に優れ、人なつこいという結果が得られました。その後の検証で、すべての子どもの発達を促すために役立つことが分かりました。
いつから始めても遅くないとのことで、私は0歳6ヶ月から始めました。
このブログでは、語りかけ育児と出会った0歳6ヶ月から2歳過ぎまで、わが家の現在進行形の様子を紹介します。2歳以降4歳までの体験談はこちらです↓
- 1日30分語りかけ育児~2歳から3歳までのやり方をまとめました【共働き家庭の体験談】
- 1日30分間「語りかけ育児」で育てた娘が4歳に!3年半の効果をまるっと公開
- 2歳4ヶ月の娘の吃音(どもり)が治るまで~症状、経過、家庭での対応の話
「語りかけ育児」との出会い
「語りかけ育児」との出会いは娘が0歳6ヶ月の頃です。
たまたまお邪魔したお友だち宅の絵本カゴに無造作に入っていたのが目に止まりました。カバーの雰囲気やタイトルが印象的だったので記憶に残ったんですよね。
子育て支援センターや図書館でも見かけ、気になりすぎて購入しました。気になる本はたいていお迎えすることになるんですが、気が合う本になることが多いです。
特別な準備が必要ない取り入れやすい育児法
「語りかけ育児」でいちばん大切なポイントは、
1日30分間はなるべく静かな環境で、子どもと向き合うことに集中し、言葉をかけて過ごす時間を作る
日中はワンオペ育児でテレビをつける習慣がなかったわが家には、静かな環境が既に備わっていたので、30分の語りかけを始めるだけでした。それ以前は特に育児法にこだわりもなく、静かな部屋でなんとなく娘と過ごしているだけだったので、簡単に取り入れられる上に娘の役に立ちそうなのはよかった。
産後1年くらいは文字を読むことに集中できなかったので、この分厚い本を全部は読みませんでしたが、娘の月齢の章を読んだその日から「語りかけ育児」を始めました。
わが家の1日30分間?「語りかけ育児」
本の通りにキッチリやると無理が出そうだったので、できる範囲でポイントだけ取り入れることにしました。
- 1日30分間、静かな環境でこどもと集中して遊ぶ時間を作る
- こどもの動作や、こどもが集中しているものごとに言葉を添える
- なるべく短く簡単な文で聞き取りやすく話す
- こどもに圧力をかけない
- 間違いはやんわり正しく言い直す(ダメ出ししない)
- 寝る前には絵本を読む時間を10分作る
上に書いたことは、始めたときから継続して取り入れています。
月齢ごとに適切な言葉のかけ方や避けた方がよい行動があるので、節目ごとに各月齢の章を読み直して、少しずつやり方を変えていってます。本全体から感じるこどもへの視線が暖かいので、読み返す度にほっこり勇気づけられるのが良いなと感じます。
1日30分間、静かな環境でこどもと集中して遊ぶ時間を作る
こどもは雑音の中から大切な音を拾い出す能力がまだ十分育っていない上に、すぐ気が散るため、静かな環境が大切
静かな環境づくりはあまり意識しなくてもできました。
元々音楽をかける習慣がなく、娘が生まれてからはなるべくテレビをつけないようにもしていた上、ワンオペ育児で昼間はこどもと2人きりなので、邪魔が入る隙はありません(笑)
難しいと感じたのは、特に0歳代、まだ赤ちゃんだった娘と30分間向き合うこと。
この時間を作るのはそう簡単ではない
本にこう書いているくらいなので、慣れるまではみんな難しいと感じるんじゃないかな。
新生児期のように、ほとんど動かず何を考えているのかさっぱり分からない感じだと語りかけのネタ探しが大変かもしれません。生後3か月未満では授乳やおむつ換えの時間を長めに取ればいいとのことで、その程度ならなんとかやっていけそうな気がします(うちは生後6ヶ月で始めたので、それ以前のことは想像の域を出ません)
生後6ヶ月頃では娘がかなり動き回るようになっていたので、娘のしていることに擬音をつけたり、娘の興味が向いたことについてしゃべったり、喃語を真似っこしてお互いに返事をしあったり、これでなんとか30分という感じでした。
30分間は娘をしっかり観察するようになったので娘の変化に気づきやすくなりました。
今日はこんなことができるようになった!という発見はほんとうに嬉しいものでした。成長につれて意思らしきものが芽生え、だんだん好奇心いっぱいになっていくのを見るのも楽しかった。
30分間を捻出できない日もありましたが、あまり気にしないことにしてました。育児はままならないことの方が多いので、60%できたら花丸です。むやみにハードル上げてもしかたない。
こどもの動作や、こどもが集中しているものごとに言葉を添える
こどもは集中している対象以外は見えていないし聞いていない
娘のの目線や指先を追って何に興味があるのか注目し、何を感じているのか表情を観察し、娘が言いたそうなことを話してみたり、娘の動作におおげさめの擬音をつけたりして遊びました。
0歳でも、自分の見ているものやしていることに大人が注目してしゃべっているのは分かるようで、チラッとこちらを見て同じ行動を続けてみたり、いったんやめて別のことを始めて大人の反応をうかがってみたり、かけひきを試みる様子がとても可愛かったです。
ちなみに擬音は娘のツボにはまるとキャッキャ言って喜んでました。
なるべく短く簡単な文で聞き取りやすく話す
こどもは複雑な文は理解できない
なるべく短い文で話す努力をしました。
大人と話すときや文章を書くときは、ひとつの文になるべく多くの情報を盛り込みたくなりますが、語りかけの時間はグッと我慢です。
主語と述語と、組み合わせても形容詞ひとつまで。おかげで、娘の目の前のものごとを言葉にする上で、根幹となる情報はどれ?枝葉はどれ?と考える機会が増えました。
声のトーンは少し高め
調子よく、ゆっくり、言葉の間に休みを入れる
赤ちゃんに話しかけるときは自然とトーンが上がるので、意識しないと上がらない人は気をつければいいんじゃないかなと。
文章のリズムを意識した結果、ゆっくり歌うように話す感じに落ち着きました。
私がしゃべるのに反応した娘がお返事をしてくれることもあるので、文と文の間も少し間を取って、娘の言葉を聞いて反応できるようにしました。
同じ単語の繰り返しを多用
聞き取りやすくするという観点で、1つの単語を、組み合わせる言葉を変えて何回も言いました。
娘がコップを持っているとき、「コップ持てたね。赤いコップだね。小さいコップだね。〇〇ちゃんのコップだね」みたいな感じ。組み合わせる言葉をひねり出すのがほんとうに大変で、大人の観察力や語彙力も問われました。子育ては修行ですね……
あかちゃん向きの特別な言い方で話しかけましょう
ここだけは私個人の価値観で、なるべく正しい文法で話し、あかちゃん言葉を使わないように気をつけました。あかちゃん時代の学習手段は音と状況のかたまりだけなので、単語と文法のサンプルは正しいに越したことはないと思ってます。大人になればあかちゃん言葉や幼児語は修正することになるので、最初から大人語を覚えた方が手間が省けるような気もするし。ただ、保育園など自宅外で覚えてくる分には気にしないスタンスです。
ちなみに、あかちゃん言葉を使わないようにした結果、保育士さんに「わんわんだよ〜」と言われて、真顔で「いぬ!」と言い放つ子どもが仕上がりました。当時2歳になる少し前。保育士さん苦笑してました。可愛げがないところが可愛いと言えば可愛いんけど、なんとも微妙な可愛さです。
アクセントと方言が盲点で、現在で娘は関西弁と私の出身地の方言が混ざった言葉を話しています。これもなんとも微妙です。ま、通じるからいいとしよう。
こどもに圧力をかけない
ここで言う圧力とは以下のようなことです。
大人のしてほしいことをこどもにさせようとする行動すべて
音や言葉を真似させたり言わせようとする
質問して答えさせようとする
遊びの最中に命令や指示をする
覚えかけの言葉をちょっと間違って発音するのはとても可愛いし、完璧に発音すればそれもまた素晴らしい。ある程度おしゃべりができるようになると、なんの気なしにした質問にたどたどしく答えてくれるのも可愛い。これはなかなか強烈な誘惑です。
私よりも夫が一時期かなりしつこく単語を練習させようとしていました。私は何度も「時期が来れば勝手に話すようになる」って言ってたんですが、それでもやる。娘がしっかり話すようになってからは飽きたようなので一安心です。
私は言葉を言わせるよりはむしろ、おもちゃで遊んでいるときに「正しい」やり方を教えたくなりました。
あかちゃんは不器用で危なっかしいし、おもちゃには製作者によって意図された遊び方があるし、ついつい指示したくなりがちです。娘は娘なりに考えて遊んでいる様子で、そのうち意図された遊び方を発見するので、グッとこらえて娘のしたいようにしてもらいました。
娘が「おかあさんやって」風の表情で持ってきたときは意図された遊び方を見せますが、娘はそれでもしたいようにしかしませんでした。コップ積みのおもちゃはまったく積まれることはなく、転がして、かじって、両手に持ってカチカチして、親が積んだものを叩いて倒して大喜びして、2歳を過ぎてからはおままごとのコップとして使われるようになりました。積んでないコップ積みの存在意義とは。
間違いはやんわり正しく言い直す(ダメ出ししない)
コミュニケーションを取ろうとするたびにいちいち言い直された結果、引っ込み思案になってしまったあかちゃんはたくさんいる
そんなことにはしてたまるかと思ったので、この点には本当に気をつけました。完璧主義なところがある私は性格上ダメ出ししがちなので……
言い直すときは鉄則である「そうね」で始める
娘の言葉が多少間違っているときは「そうね、イチ…イチ……、いちごがほしいのかな?」のように言い直し、娘の表情を観察しました。娘がニッコリしたら正解なので「そっか、いちごがほしいのね。いちごおいしいよね」と繰り返し。ちょっぴり内容を膨らませると嬉しいみたいです。
まだ言葉があまり出ない頃の娘は、私が外すと露骨にガッカリした顔をして指差しで教えてくれました。言葉が達者になってからは「チガウ!チガウ!それじゃないの!」と容赦ないダメ出しをしてくれてます。たまに泣く。ほんと2歳児って母親にはキビしい……。
気をつけた成果かどうかは分かりませんが、娘はおしゃべりが大好きです。
わりと警戒心が強く、臆病なところもある慎重派の娘ですが、おしゃべりについてはまったく引っ込み思案な様子は感じられません。新しい言葉やものごとは、とりあえず言ってみて、大人の反応を見てニンマリ、時々ガッカリしたり怒ったり。保育園でもあれやこれやと先生におしゃべりしているらしく、つきあってくれる先生方には頭が上がりません。
寝る前には絵本を読む時間を10分作る
わが家では毎晩の寝かしつけの前に絵本を読み聞かせています。
大人の語彙には偏りがあり、日常で体験できることも限られているので、子どもの世界を広げるために絵本はとてもよいものです。想像の翼が広がるとよいなと思ってます。
娘が言葉を発するようになるまで分からなかったのですが、子どもはものすごい勢いで絵本の内容を覚えるものですね。
2歳を過ぎてからは、だいたい3〜4日も集中して読みきかせれば、断片的ながらも印象的な場面を覚えていて、私に読み聞かせしてくれるようになりました。私が読もうとしても、自分で読みたいときは「よまないで!イヤ!」って怒ります。そしてすっごく得意げに読みます。
絵本が好きになったことで、「そろそろおふとんで絵本読むよー」と言うと、「はいっ!」といいお返事で寝室に移動してくれるというおまけがつきました。
保育所の本の貸出日や図書館に行った日は、帰ってすぐに何回か読みきかせないと家事をさせてくれないことだけが難点です。
これまで娘に読み聞かせた本は楽天ROOMにも載せています。
→TsumuRiの楽天ROOM
2歳までの「語りかけ育児」の結果と今後の課題
「語りかけ育児」をやってみてよかったこと
いちばんよかったのは、親であるわたし自身が変われたことです。
「語りかけ育児」は、子どもを変えるための育児法ではなく、まず親が変わることで見える世界や子どもとの関わり方が変わって、結果的に子どもも変わるというか。
私が娘のの興味に視線を向けるようになったことで、娘の意思や表情の変化に気づくことが増えて、結果的に娘とコミュニケーションを取りやすくなり、娘の成長や変化にも気づくようになったりしたんじゃないかなと。
そうやって密な関わりの時間を作ることで、娘がほんとうに嬉しそうな表情をしてくれるのもよかったと思います。昼間働いていると、どうしても片手間で相手をすることが増えてしまいますが、しっかり向き合った時はやっぱり表情が違うと感じています。
エビデンスがあるという「語りかけ育児」の効果については何とも言えません。
娘は保育園の先生が驚くくらい言葉が早かったですが、1ヶ月早く生まれた娘のいとこも娘と同じくらいにおしゃべりさんなので、育児法じゃなくて血筋なんじゃないかなと。
聞くことへの集中力や話す意欲はしっかり育っているので、できる範囲で試してみるだけの価値はあるとは思います。
「語りかけ育児」をしたからと言って、言葉の発達面でまったく心配事がないわけではありません。
2歳4ヶ月頃から少し吃音が出始めました。保育園の先生にはこの時期ではよくあることと聞いていますし、本の中でも言葉の正常な発達の過程で見られることとあったので、これまでと同じような「語りかけ育児」の関わりを続けています。
詳しくはこちらに書いています
→2歳4ヶ月の娘の吃音(どもり)が治るまで~症状、経過、家庭での対応の話
育休終了後の課題:時間の確保とテレビ問題
育休終了後は、まとめて30分を取ることが難しくなってきました。
保育園の行き帰りの自転車でのおしゃべり、お風呂から寝るまでの時間、寝かしつけ前の絵本の読み聞かせ、合わせてなんとか30分を超えるくらい。
あと気になるのはテレビの視聴時間ですよね。本人が一緒に見たがるので、なるべく一緒には見ながらおしゃべりしてますが、平日帰宅してから寝かしつけまでの3時間の持ち時間の中で、見せすぎにならないようバランスを取ろうと模索してます。
それでも娘がほんとうに嬉しそうな顔をしてくれるので、これからもできる範囲で続けるつもりです。
最後に
書籍「語りかけ育児」の紹介
最後に書籍「語りかけ育児」をあらためて紹介します。
著者は、イギリスの言語治療士サリー・ウォードさん。
元々は言葉に遅れや障害を持つこどものために開発した方法を、0歳代のごく幼いこどもに応用したもので、子どもの言葉を豊かに育てるエビデンスがあります。
書籍の内容は、乳幼児の月齢ごとの成長の様子、月齢に応じた語りかけ育児の方法、おすすめの遊び、言葉の成長に気がかりのある子どもが語りかけ育児によって変化する実例など盛り沢山。一般向けの育児書の中では文字が多く、400ページ程度とボリュームもあります。
文章は易しいので、わりとすらすら読めますし、読み物としてもおもしろいです。
産後は一度に全部読む時間を取りにくいと思いますので、子どもの成長に合わせて必要な部分だけを読み、今日からの育児に取り入れるのが、私のおすすめの読み方です。
言葉の発達は個人差が大きいので、月齢にこだわりすぎず子どもの様子を見てちょうどいいところから試してみるのがいいと思います。月齢ごとに「ことばの発達」の項目があるので、目安になると思いますよ。書籍に「語りかけ育児を実践しているこどもは」という表現がところどころ出てくるあたり、ある程度大きくなってから「語りかけ育児」を始めるお子さんの場合は、少し戻って始めることになるかもしれません。
初めての方は無料のお試し特別版を見てみるとよいと思います♡
告知:小学館にインタビューが掲載されました
小学館の子育てメディアHugKumから「語りかけ育児」について取材を受けました。
「語りかけ育児」を紹介する全3回の記事で、第1回、第2回には、実践する際のポイントがコンパクトにまとめられています。体験談は第3回として記事にまとめていただきました。
その後の語りかけ育児
2歳以降の語りかけ育児についてはこちらにまとめました。合わせてどうぞ