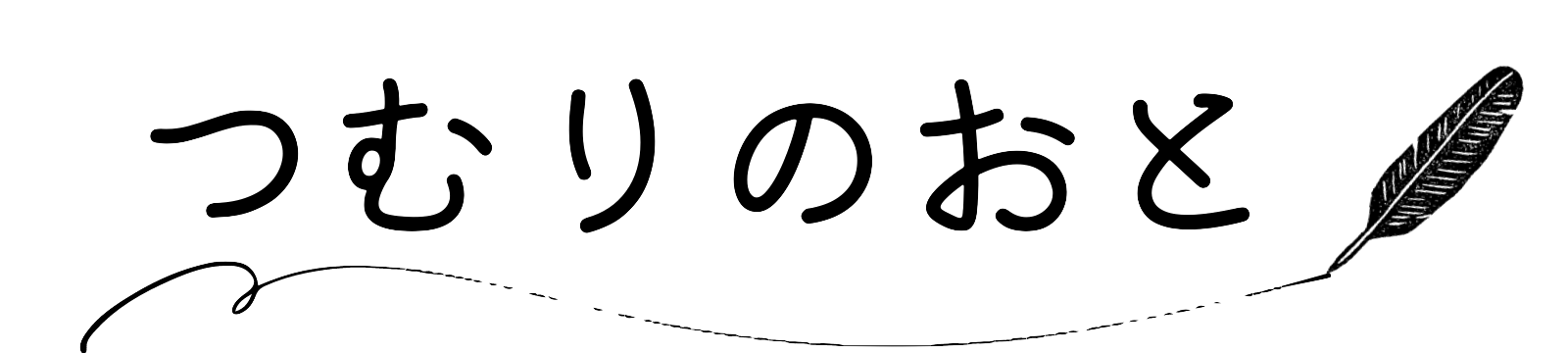こんにちは、つむりです。
年中児(5歳)の娘の自転車の補助輪を外しました。
最近は3歳や4歳の子でも補助輪なし自転車をスイスイ乗り回しているので、娘は遅い方だと思いますが、本人が補助輪を外すことを怖がっていたし、保育園を卒園するまでは自転車に乗れなくても困らないので、気長に構えてました。
……ところが5歳9ヶ月のある日。
ちょっとしたきっかけで練習する気になった娘が、1時間足らずで補助輪なし自転車を乗り回すようになったので、夫も私もビックリ!夫婦ともに小学校に上がるまで補助輪を外せず、何度も転んで練習したタイプなので……
今回は、娘の自転車の補助輪がスムーズに外れた理由として思い当たることを紹介しますね。
三輪車や補助輪つき自転車を乗り回していた
2歳で三輪車、3歳でストライダー、4歳で補助輪つき自転車(16インチ)を買いました。
三輪車は漕ぐのにパワーが必要なので乗れるようになったのは3歳過ぎ。その頃からは親が小走りで追いかけるほどのスピードで爆走してました。
娘の三輪車はこちらで詳しく紹介しています(廃番品)↓
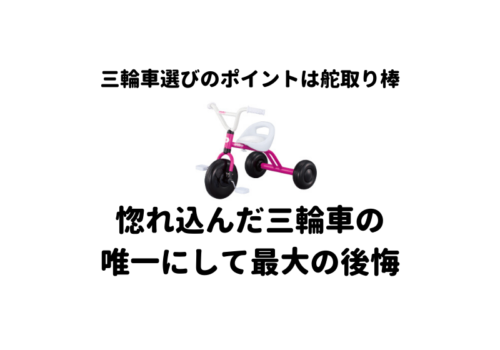
自転車はアイデスの16インチ。柄以外はこれ(↓)と同じものです。
三輪車に比べると補助輪つき自転車は左右にグラつくので、初めのうち娘は怖がりました。ただ、同じ団地内の子どもが補助輪なし自転車で走り回っているのに刺激を受け、すぐに乗り回すようになりました。三輪車より補助輪つき自転車の方が楽に漕げてスピードも出ます。補助輪つき自転車に慣れると三輪車には乗らなくなりました。
この期間にペダルを漕ぐ動作やブレーキ操作に慣れることができたので、早いうちから乗せておいて良かったと思います。
ストライダー(キックバイク)を乗り回していた
ストライダーなどキックバイクは1歳頃から乗れますし、補助輪なし自転車のバランス感覚を養うにもよいと言われるので、最近は三輪車や自転車より先に買うことも多いですよね。
わが家もバランス感覚を養うとの触れ込みに惹かれて娘が3歳の時にストライダーを買いましたが、娘は「グラグラして怖い」とあまり乗りませんでした。安定を好む娘よ……結局、3歳のうちは乗りこなせず、4歳を過ぎてからお友だちに刺激を受け、教えてもらって乗り回すようになりました。
二輪のバランス感覚や、転びそうになった時に足をつくことをこの時期に覚えたので、乗り回した期間は短いけど買ってよかったです。
うちの娘のように、ストライダーの倒れやすさを嫌がる子は三輪車や補助輪つき自転車から始めるのがおすすめです。
乗せてみないと分からないんだけどw
娘本人が補助輪なし自転車に乗る気になった
ここまでできるようになっても、自転車の補助輪を外すまでに1年の空白がありました。
理由は本人の恐怖心。娘が「グラグラして怖いから補助輪取っちゃダメ」と言い張ったので補助輪を外すきっかけがなかったのです。
親としてはストライダーも自転車も補助輪がないのは同じだと思いましたが、怖さを感じるとなかなか先に進まない娘なので、本人がやる気になるまで待ちました。
……離乳食の進みもおむつ外れも遅かったので、待つことには慣れてます。
きっかけは道路交通規則!小学校入学後は自転車に同乗できない
道路交通規則等で、自転車に同乗させてよいのは小学校入学前までということはご存知です?
自転車の幼児用座席に乗せることができる子どもの年齢制限が、46都道府県で「6歳未満」から「小学校入学まで」に緩和された。以前は、子どもを自転車で幼稚園や保育園に送迎していても、年長の時に6歳になると乗せることができなかったため、緩和を求める声が上がっていた。
大手小町|いつまで乗せていいの? 自転車幼児座席の年齢制限が変わった
※2022年1月現在、47都道府県で「小学校入学まで」に緩和されている(参考)
※最新の状況は各県警のホームページをご確認ください
うちの娘はこれがきっかけで補助輪を外す気になりました。
小学生になったら自転車の後ろに乗れないって法律で決まってるらしいよ?補助輪つきで道路走るのも怖いし、どうしよう?
補助輪のない自転車買ってもらえばいいよ!可愛いやつ!やったー!
補助輪がないと乗れない子には補助輪なし自転車は買えないよ?乗れるか分からんもん
わかった!特訓する!
それなら安心して補助輪のない自転車買えるし、一緒にあちこちお出かけできて楽しいね
娘にとって、
- 小学生になるまでに補助輪を外せないとお出かけに困る
- 補助輪なしの自転車に乗れれば楽しくお出かけできる
- 補助輪なしの自転車に乗れたら新しい自転車(可愛い)を買える
これらが怖さに打ち勝つ強いモチベーションになったようです。道路交通規則がきっかけって、わが娘ながらクソ真面目かって思いますけどね……
身体面のポテンシャルがあっても、本人が望まなければ補助輪を外すのは難しいので、毎日の暮らしの中できっかけを提示することが大切と感じました。
また、自転車中心の生活なら、年中の後半から年長に上がる時期にかけて、小学校入学後の移動手段について考えておくといいと思います。1年あれば余裕を持って対応できるので。
広いスペースでのびのび練習した
練習場所は広いに越したことはありません。安心感が違う。
娘は保育園で「駐車場では自転車の練習をしない」と指導されており、娘本人が広いグラウンドで練習することを望みました。やはりクソ真面目です、娘。君は正しい。
だだっ広くて人がいなくて自由に使えるグラウンドで練習することにしました。
娘は漕ぎ出しでよろけることが多く、ストライダーの要領で足で地面を蹴って勢いをつけてからペダルを漕ぎます。特に初めのうちは、足をついたまま10mくらい走ってました。助走が長い……!
また、補助輪つき自転車では曲がれるのに補助輪を取るとなぜか曲がれず、ひたすらまっすぐ漕いで、グラウンドの端のフェンスにぶつかる直前で止まることを繰り返していました。
練習場所が狭いと、
- ペダルを漕ぎはじめる前に止まる
- 乗れたと思ったら曲がるために止まる
こういう状態だとなかなか乗るところまでいかないので、特に初めの頃ほど広い場所で練習することが大切と感じました。
これは失敗だったかも?自転車が重かった
唯一、自転車の重量は買う時にもう少し考えたほうが良かったかな?と思いました。
補助輪を外した直後に娘本人から「ストライダーより重たい!グラグラして怖い!」との言葉を聞いたので…
確かに、ストライダーは約3kg、娘の自転車は15kgと重さがまったく違うし、サイズが異なるので車体のバランスも異なります。
子どもは大人より身体が小さく力がないので、補助輪のない自転車を止まった状態で支えたり倒れた状態から起こしたりするのは、大人が考える以上に大変なのです(よく考えると、15kgって小柄な子どもの体重と変わりません)
また、自転車が軽い方が漕ぎはじめが楽なので、これからお子さまの自転車を選ぶ皆さんはぜひ自転車の重さにも注目してみてください。最近はペダルを後付けできるキックバイクが増えていて、自転車に比べるとはるかに軽いことや、小さい頃から遊び慣れたものを続けて使えることがよいと思います。
娘のお友だちはへんしんバイクに乗っている子が多かったです。

ちなみにストライダーにもペダルを後付けできる14インチモデルが出ています。
娘が3歳の頃は未発売だったけど、あったらこっちにしてたと思う
最後に:わが家は子どものペースにまかせて大丈夫でした
娘の補助輪を外してから娘が補助輪なし自転車に乗れるようになるまで、夫も私も何も教えませんでした。
娘をグラウンドに連れて行き、練習してるのを眺めながら、娘が色々言ってくるのに応答してたくらいで、完全に娘に丸投げです(笑)
娘の自転車の補助輪を外してスタンドをつけるくらいはしたけど、それって指導ではないしなぁ……
キックバイク、三輪車、補助輪つき自転車でしっかり遊んでいればポテンシャルは十分なので、やる気になるタイミングを待てばスムーズに補助輪を外せると感じました。
おしまい。