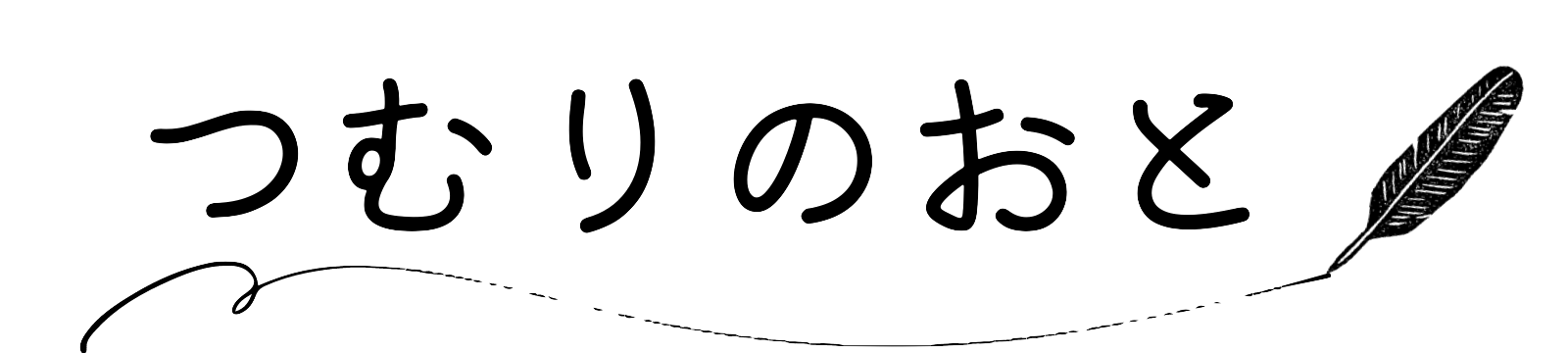こんにちは、つむり @TsumuRi です。
2018年10月25日、26日と、京都で開催されたJTF翻訳祭2018に参加しました。
とても充実した2日間でしたので、熱が冷めないうちに記録を残しておこうと思います。
例によって長~~~い記事になりますが、お付き合いいただければ幸いです。
JTF翻訳祭2018の概要
JTF翻訳祭とは、日本翻訳連盟(JTF)が主催する翻訳業界のお祭りです。
翻訳業界関係者が全国から集まり、講演会、パネルディスカッション、交流会などを行います。
例年、東京で開催していましたが、2018年はなんと京都開催でした。
- 開催日:10月25日(木)、10月26日(金)
- 開催地:京都市
- 参加費:JTF会員 7,000円、非会員 10,000円 (2日間有効)
支払い手段はクレジットカードと振込ですが、請求書での支払いも可能というところに翻訳業界ぽさを感じました……
大阪在住の私にとって京都はアクセスが容易なエリア。とてもよい機会なので、2日間とも参加しました。
JTF翻訳祭2018初参加の感想
やっぱり「言葉」が大好き!
聴講したセッションは、いずれも興味深く、集中して聞き入ってしまいました。さすがは日本最大の翻訳業界のお祭りです。
特に1日目は仕事でも日常生活でも関わりのある「言葉を使う」行為について、深く考えさせられるものでした。
やっぱり「言葉」が大好きだとしみじみ思いました
メインテーマは把握しておきたい
翻訳祭終了後にブログやTwitterを見ると、今回のメインテーマである機械翻訳の話題がかなり盛り上がっていた(炎上?)ので、少なくとも1つは聴講しておくべきだったと反省しました。
実務で機械翻訳を使っているのに意識が低かったと猛反省しております
気になるコングレスバッグの中身を紹介

コングレスバッグの中身は、抄録集やJTF会誌、ほんやく検定の案内など。京都観光案内もありますね。他はサポーター企業のパンフレットなど広告です。撮り忘れましたが名札もありました。
JTF会誌と通訳翻訳キャリアガイドが嬉しかったです!
聴講セッションの紹介&感想
私が聴講したセッションを紹介します。
個人的なノートを元にしているため、私の主観がかなり入っていることを悪しからずご了承ください。
わりと「書きすぎる」方ではある私ですが、セッションのライヴ感や間の妙味まではお伝えできなくて悔しいです。
分かりやすいことばと難しいことば
三省堂国語辞典の編集委員、飯間浩明氏(@IIMA_Hiroaki)による、「分かりやすいことば」についてのセッションです。
飯間さんの言葉そのものや辞書の編纂に対する熱い想いが溢れていて、これまで仕事の道具に過ぎなかった辞書が急に愛しく感じられました。いわゆる「言葉の乱れ」についても「新しい言葉」と捉え、言葉の変化に優しい眼差しを向けていらっしゃるのが印象的でした。
講演でアドバイスいただいたとおり日常的に文章を書くときは「中学生が読んでも分かる」ことを目指すようにしようと思います。
ほんとうにこのセッションは熱くてですね、すっかり忘れていた古い記憶が呼び起こされるくらいでした。
分かりやすい文章のための辞書活用法
翻訳に限らず日常的に役立つお話だったので、お話のポイントをまとめてみました。
分かりにくさの原因をレベル分けすると「単語」「文法」「構成」の3つのレベルに分けられます。
| レベル | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 単語レベル | 難しい単語を選んでいる | 易しい単語を選ぶ |
| 文法レベル | 読者が想定している文法から外れている | 標準的な文法に基づいて書く |
| 構成レベル | 構成がまずい | 構成を見直す(特に、結論は先に!) |
単語については、易しいものを選ぶためのヒントとして「三省堂国語辞典 第七版」の工夫が紹介されました。
三省堂国語辞典は、単語の後に〔話〕〔文〕〔俗〕〔古〕などの表示(位相の表示)をしています。
- 表示なし⇒日常語(三省堂ホームページでは「基本語」と表記されています)
- 〔話〕⇒話し言葉
- 〔文〕⇒文章語
- 〔俗〕⇒俗語
- 〔古〕⇒古語
単語を選ぶ際は、会話では「日常語」と「話し言葉」、文章では「日常語」と「文章語」が目安になるとのことでした。
表示は、三省堂ホームページの「なかみを見る」や「宣伝用パンフレット」で確認できますよ。
日常語と文章語の間にハッキリした基準がないため「向井理が喋りそうかどうか」を基準にしたというエピソードが頭から離れません……
用語集の重要性と運用の在り方
パネルディスカッション形式で3名が登壇しました。
- クライアント視点:徳田直樹氏(テクニカルコミュニケーター協会)
- 翻訳会社視点:森口功造氏(JTF理事、川村インターナショナル)
- 個人翻訳者視点:高橋聡氏(通称帽子屋さん、JTF理事、個人翻訳者)
ドイツでの用語集の標準化の実例と、日本の現状(標準化が遅れているため、それぞれの立場でみんなが困っている)、さらに打開策としてのJTFの取り組みが紹介されました。
わたしは翻訳(技術文書)の用語集をあくまで辞書の枠組みで捉えていたのですが、このセッションを聞いて、用語集はクライアント・翻訳会社・翻訳者のためのコミュニケーションツールでもあるという意識に変わりました。
そんなに大切なものでありながら、現状はわたしが仕事の合間に作った用語集をちょっと貸してと言われることもある状況なんですよね……
どういうアプローチが取れるかは全くノープランですが、このような状況が少しはマシになるように行動したいなと思いました。
iPS細胞を用いたパーキンソン病治療
京都大学iPS細胞研究所教授、高橋淳氏による、iPS細胞を用いた再生医療についてのセッションです。
日本でいちばん分かりやすいiPS細胞の紹介だったと個人的には思います。
レベル感は、Eテレの夜の番組を想像していただければ当たらずとも遠からずかと
そもそもの「治癒」の定義から、生体内の事象のメカニズム、パーキンソン病の病態、iPS細胞の作製/選別方法など、ほんとうに易しく分かりやすい解説でした。この講演の後に教科書を読めば、迷子になるのは避けられるはず。
iPS細胞のパーキンソン病への臨床応用については、基礎研究や前臨床の研究結果と、2018年10月現在実施中の臨床試験の概要の説明がありました。研究所のプレスリリースでも見られます。

製造工程の管理や規格試験については口頭での詳細な説明はありませんでしたが、スライドに管理項目を入れてくださったのが個人的にはとても嬉しかったです。医薬翻訳の花形は臨床分野で、品質分野はどうも影が薄いと勝手に拗ねている私なのでした。
memoQのここが好き!翻訳者・PM・トレーナーがmemoQの強みと便利な機能を語ります!
翻訳メモリmemoQのよいところを、愛用者の皆さんとメーカーの担当者さんが語ってくださいました。
- 翻訳会社視点:マイアットかおり氏
- 翻訳者視点:糸目慈樹氏
- トレーナー視点:Angelika Zerfass氏
- 司会進行:三浦曜氏(memoQ)
ランチョンということもあり、和気藹々とした雰囲気でした。
memoQの操作については最初にさらりと説明された程度ですが、他の翻訳メモリを使ったことがあれば直感的に使えそうでした。
memoQの特徴は強力なQAツールで、クラウド版はさらに進捗管理機能や版管理機能もあり、翻訳者も翻訳会社も便利だということが強調されていました。
でも、翻訳会社側のメリットは翻訳者にとっては良かれ悪しかれ。さぼったりやらかしたりしたらバレます。いや、サボる気ないけどさ……
他のツールと比較して動作が軽いことや、学習環境が充実していることもメリットとして挙げられていました。
セッション中に紹介された「翻訳祭限定20%OFFクーポンコード」(期限あり)は抄録集のmemoQの広告ページにあります。実はアメリア会員割引の方が大きい(30%OFF)ので会員の方は要チェックです。

Road to XV ~FINAL FANTASY XVで12言語を同時発売出来るまで~
登壇者はFFXVの開発にも関わった、株式会社Luminous Productionsの長谷川勇氏。
言わずと知れた、スクウェア・エニックスの有名ゲームタイトルファイナルファンタジーXV(FFXV)の12言語同時発売を支えた翻訳プロセスに関するセッションです。
プロジェクタの大画面でゲームのトレーラーを見てワクワクが止まらない状態に。痺れました……!
興味のある方はぜひ、公式サイトのトレーラーをご覧になってくださいね。
登壇者の長谷川勇氏は、プログラミング面からFFXVの開発に関わったということで、プログラマー視点の裏話をたくさん聞かせていただきました。テキスト翻訳の管理システム「Byblos」については、ゲーム業界のカンファレンス「CEDEC2017」にて詳しいお話しをされたそうで、翻訳祭のセッションでは名前が出ただけでした。
本セッションでは、FFXVにおける翻訳への強いこだわりを感じました。
英語版では、キャラの個性に合わせて南部訛りにしたりブリティッシュイングリッシュにしたりと、変化をつけたそうです。
ゲームは音声収録やアニメーションがあるため、収録方法によっては尺の長さを合わせるだけでは済まず、無音の時間帯や母音を日本語に合わせて調整することにより唇の動きのアニメーションが不自然にならないようにすることもあるそうで、並々ならぬ努力を感じました。
さらに、テキストが単純に翻訳されていればよいというわけではありません。日本語には存在しない「単数形/複数形」や「男性形/女性形」を適切にゲーム画面上に出力するための設計をしたり、各国の文化や規制に応じてビジュアル表現を変更するということもされたそうです。
長々書きましたが、ほんとうに、言語周りの作り込みがすごいゲームだということが分かりました!
ただのゲーマー的感想ですいません!ついでに言うとFFXVでもシドが健在で嬉しかったです。でも中国版の全身タイツのシヴァは……(自粛)
元・翻訳コーディネータからのアドバイス
駆け出し翻訳者の段階を抜け出すための方法論のお話でした。
登壇者の酒井秀介氏は翻訳者・通訳者向けにマーケティング戦略をコーチされている方で、翻訳者にとって高い翻訳力は前提であり、これをさらに伸ばすよりもマーケティング戦略を取り入れる方が売上獲得には効果的という切り口でお話をされていました。
このセッションの結論は「稼ぐと決めて行動する」、これに尽きます。
行動のための具体的な目標設定の方法(現在が10なら目標は12~13に設定すると達成が易しくモチベーション維持に繋がる)や、行動のひとつとしてエージェントへの登録戦略が紹介されました。
登録先を決める段階では自分軸で考えるんですが、翻訳会社へのアプローチ段階では相手軸で表現するだけでも変わるとか。
マーケティングってほんまに心理学ですよね
翻訳者にとってのブログ運営
時間の都合で翻訳者としてブログを書くメリットや、パラレルキャリアの話が割愛されたのは残念でした。
ただ、それまでのお話の中でヒントはかなり出てまして、セルフブランディングの手段や、翻訳会社を介さないアプローチ経路としてのブログのお話を予定されていたのかしらと、勝手に推測しています。勝手に。
ただ、ブログは何でも書ける分、気をつけないと逆ブランディングにもなるのが怖いところだとも思います。
当ブログは「子どもと過ごす日々の暮らし」を軸に、ゆる~く運営しておりますよ!
聴講していないけど気になったセッション
翻訳祭後のブログやTwitterを見て、やっぱり聴講しておけばよかったと思ったセッションを紹介します。
あなたがつくる医学翻訳の未来:Prescription for Survival続編
私自身が医薬翻訳に携わる機械翻訳ユーザーなのだから、現場を目撃すべきでした。
そう思ったきっかけがこちらのTwitterです。
機械翻訳が作った醤油ラーメンをクライアントがとんこつラーメンラーメン食べたいから人間が直すって例えはどうなの?
— カンサン (@kansankansan) October 26, 2018
後日、ブログにまとめてくださってました。
私自身はセッションを聴講していないのでセッション自体については何も語れませんが、機械翻訳についての所感を。
私個人としては、「機械翻訳の方がいい案件」や「機械翻訳でいい案件」は機械におまかせして人間のなすべきことに集中したいと考えます。
原文の執筆者が原文に込めたニュアンスを背景から読み解けるのは(まだ当分は)人間の翻訳者だけですし、機械が今後それをできるように開発あるいは教育していくのも(まだ当分は)人間の役目なんですよね。
機械と人間の住み分けはもう始まっていると日々の実務の中で感じていますが、私は共存の先によりよき未来を見たいです。
でも、精度の低すぎる機械の尻拭いはちょっと辞退させていただきたいです!
JTF翻訳祭2018に初参加した覚え書き
初めての参加ということで、実は検索しても分からなかったことや、そもそも想定していなかったこともありました。
覚え書きとしてまとめておきます。
申し込みや座席は先着順
申し込みはEventResistというシステムを使いました。
申し込み段階で、翻訳祭自体の参加と聴講予定のセッションを事前登録しました。この段階で聴講予定のセッションが満席になっていても、これはあくまで席数のカウント目的です。翻訳祭当日は、完全入れ替え制の先着順で座席を確保するシステムだったので、当日の座席が空いていれば入れました。
なお、翻訳祭の参加登録自体ができなかった場合の当日受付はありませんでした。
EventResistのアプリが便利だった
参加登録の受付メールには、添付のPDFを印刷して持参するよう案内がありましたが、実際はEventResistのアプリでも受付できました。アプリから翻訳祭に関する公式情報がほぼリンクされていて便利でした。T
翻訳祭のFacebookページの存在をアプリで知ったわたしです!
欲を言えば、アプリ上で各セッションの会場が分かればもっと良かったです。
アプリから翻訳祭2018の公式サイトへリンクがあるのでセッション会場はスマホで確認できます。また、紙のパンフレットでも分かります。でも、こんなに便利なものがあるとワンタップで確認できることを期待してしまうんです(笑)
事前の情報収集はブログやTwitterで!
初参加で右も左も分からなかったので、事前にブログでここ数年の情報を、Twitterで最新情報を収集しました。
運営委員の方がTwitterで情報発信してくださっており、ほんとうにありがたかったです。
また、申し込み後から当日まで、Twitterの表示名を「TsumuRi@10/25,26翻訳祭初参加」にしていたところ、フォローいただける方が増えました。
ありがとうございます!
でも、これ私のほんとうにダメなところだと思うんですが、参加される方にもっとTwitterで話しかけてみたらよかったと思います。
筆記用具とノート(手帳)は必須
お土産の写真を見てわかる通り、筆記用具とノートは入っていません。
また、聴講したセッションの半分以上は配布資料がありませんでした。広報を兼ねた演題は配布資料がある印象です。
したがって、筆記用具とノートは必須だと思われます。
まあ「ノートを取るヤツはバカだ」なんて話も出ましたけどね~。ちなみにわたしはノート魔です
わたしはうっかりノートを忘れてしまい、ほぼ日手帳の空いているページを使いました。座席にテーブルがついてなかったので、厚みとコンパクトさが丁度よかったです。
参加者の服装はけっこうバラバラ
参加者の服装は、スーツの方からTシャツの方までバラバラでした。和服をお召しの方も数名いらっしゃって、とても素敵でした!
個人的な感想ですが、セッション聴講だけなら最低限オフィスカジュアルを意識すれば浮くことはないと思います。
実際、会社に出勤する格好で出向いたわたしです。
名刺は必須
Twitterでアドバイスいただいたことを受けて、名刺を作成しました。
お話しする機会をいただけた方は、皆さん名刺をお持ちでしたので、用意しておいて本当によかったです。
名刺作成の紆余曲折は別の記事にまとめました。

でも、至らなかったなあと思うところもやっぱりいくつかあったんですよ……
今回の参加は会社の業務ではありません。さらに私は個人事業主でもないので、同業者さんとの交流用と考え、最低限の連絡先情報に絞った名刺を作成したんですね。いわゆるSNS名刺というやつです。もちろん日本語のみ。
でも、実際に参加するとこんな場面がありました。
- 企業ブースで住所や電話番号を書く機会があってモタモタした
⇒連絡先情報全部入りの名刺も作っておけばよかった - 海外の翻訳会社さんに声をかけていただいた
⇒英語版やバイリンガル版も考えておけばよかった
全部カバーしようと思うとキリがありませんが、まだまだ工夫の余地はありそうです。
英会話をもっとやっとけばよかった
企業ブースで海外の翻訳会社さんに声をかけていただいたんですが、予想していなかったので驚きました。
よくよく考えれば、英語話者がいて当たり前の世界なんですけどね……。
日常的には英会話が必要ない(時々英語の会議がある程度)わりに、意外と話せてホッとしましたが、直前に英会話をやっておけば、もっとつっこんだお話もできたのかもしれません。
こんな仕事をしているくせに、英語に悩んでいるわたしです。いつになったら悩まなくなるんでしょうね?
翻訳祭2019は横浜です!
このような集会や勉強会に参加すること自体が3年ぶりくらいということもあり、ほんとうに楽しかったです。
翻訳祭にはまた参加したいし、近郊の勉強会にも少しずつ参加して、言葉を磨きたいと強く思いました。
次回、翻訳祭2019(第29回)は、横浜で開催する予定だということです。
……遠征……できるのか?!(ゴクリ)
最後になりましたが、当日お話しする時間をいただいた皆様、こんなに素敵な時間を過ごす機会を作ってくださった実行委員の皆様、ほんとうにありがとうございました!
そして、この長い長いラブレターに最後までお付き合いくださり、ほんとうにありがとうございました。