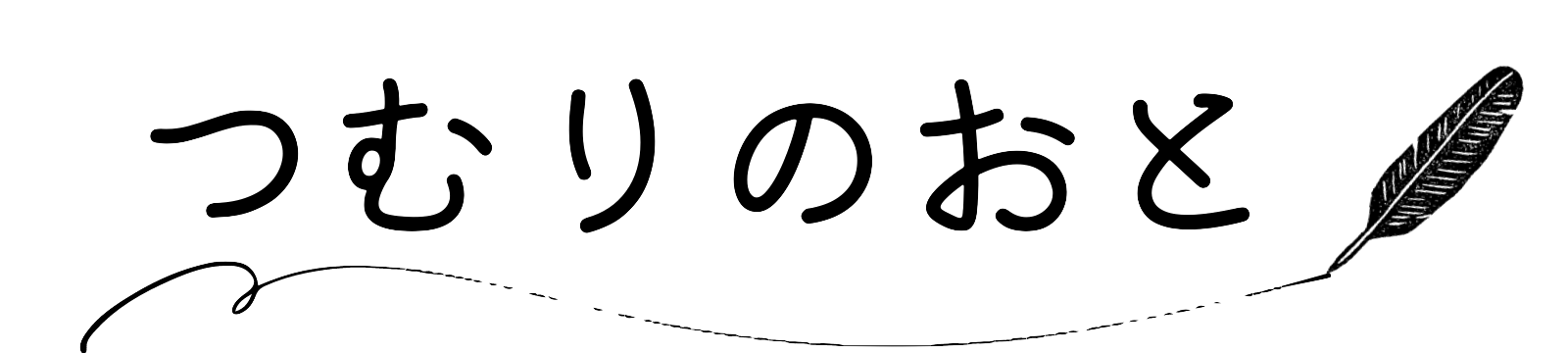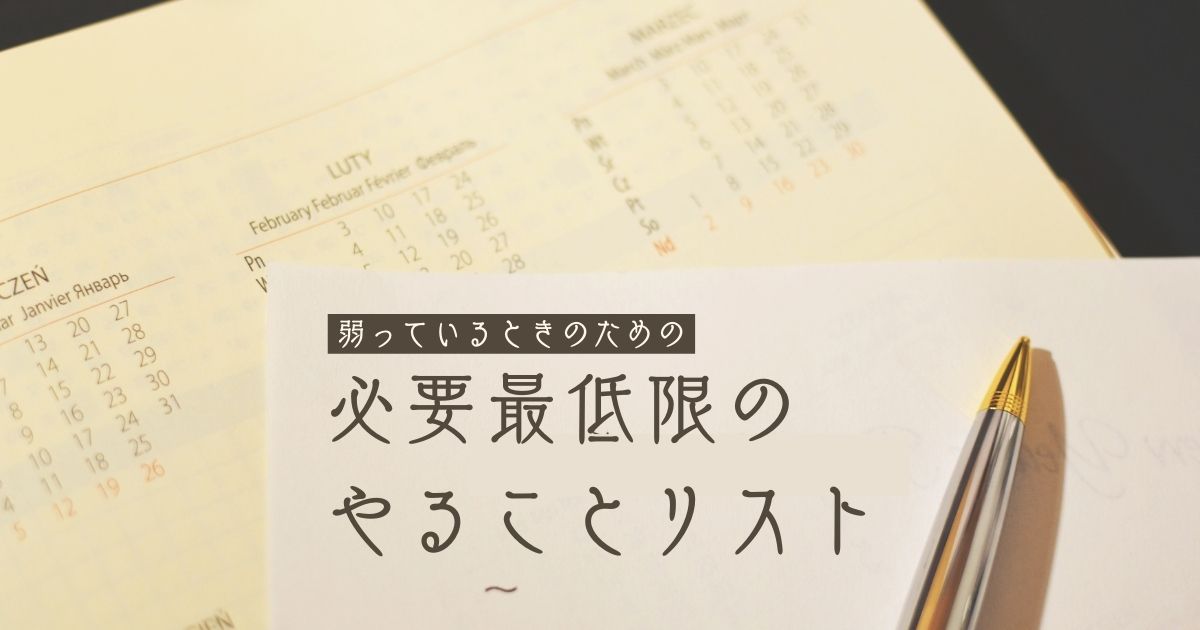こんにちは、つむり @TsumuRi です。
このところ、忙しい上に睡眠不足が重なって疲れており、娘との関係にも悪影響が出てきたように感じていたので、久々に「本当に弱っている時のための必要最低限のやることリスト」を引っ張り出しました。
私のやることリスト
— つむり (@TsumuRi) September 5, 2019
(ver.ほんまに弱ってるとき)
◆やること
□食べる(お惣菜や冷食OK)
□寝る(眠れたら眠る)
□出す
◆やれたらやること
□ボーっとする
□朝の日光を浴びる
□ストレッチ
□散歩(5分)
□風呂
□洗濯
□掃除
◆やらないこと
□インターネット
□人づきあい
□
□
この「必要最低限のやることリスト」は、私がメンタル不調で休職していた頃に精神科の主治医から「休養以外のことは一切しないよう」に指示されたことを受け、「休養以外は何もしない」を実行するために作りました。ほんとうに弱っているときには役立つのでシェアしますね。
本当に弱っているときのやることリストの活用法
ほんとうに弱っている時のやることリストは、キレイには作りません。
当時の手帳が真っ白だったので、ウイークリーページにざっくりと欄を作り、できたことだけスタンプで印をつけて生活していました。
最低限「やること」を全部埋める
大前提として、このリストは休養のためのリストです。
よって、最低限「やること」をクリアできればOKですし、スタンプを押す判定もゆるゆるです。
- 食べる:食べればOK(自炊じゃなくてもコンビニやレトルトや冷食でもOK)
- 寝る:夜に布団で横になっていればOK(全く眠れなくてもOK)
- 出す:トイレに座れればOK(快便じゃなくてもOK)
最低限これだけでも「休養する」ことはできます。
食事は本当はバランスを考えた方がよいのですが、味さえ分からなかった時期はカロリーと水分が入ればよしとしていました。
諸説ありますが、かの有名な一休宗純はこんな歌を詠んだそうです。
世の中は起きて箱して(糞して)寝て食って後は死ぬを待つばかりなり
Wikipedia – 一休宗純
少し違ったバージョンで「人生は食て寝て起きて糞垂れて子は親となる子は親となる」という歌もあります。
人間の生物としての本質は「食う」「出す」「寝る」程度で、それ以外のことはお飾りですし、本当に弱っているときくらいは手放しちゃっても大丈夫ですよ。元気になれば取り戻せます。
「やること」に集中するため「やらないこと」を断ち切る
休養を極めるためには活動量を削ることも必要です。ただ、これが案外難しいのでリストの力を借ります。
「生存に不要なこと(=やらないこと)」をリストアップして活動量を減らし、浮いた時間・気力・体力を「生存に必要なこと(=やること)」に振り分けていくイメージです。
なにをカットするかは人によりますが、「時間・気力・体力を大きく消耗すること」や「心身によくないこと」の中から「期限が差し迫っておらず」「必要性が低く」「重要度が低い」ものを選んだ結果、以下2つの物事を削ることにしました。
- インターネット
- 人づきあい
だらだらネットを見ると睡眠時間が減ったり不安になったりしますし、弱っているときは人とのやりとりで消耗して落ち込むことが多いんですよね。療養中だけと割り切ってバッサリ削ることにしました。
習慣になっているものをやめると最初はムズムズしますが、重要性が低ければ1週間くらいで慣れると思います。当時は気力も体力もなかったので、手放して楽になった時点で「もうどうでもいいや」と思えました。
エッセンシャル思考を突き詰めるとこうなるのかも
エッセンシャル思考は本当に必要なことを選択して他のことを手放し、リソースを必要なことに集中して達成していくことを勧める考え方です。断捨離にも通じるところがあると思います。やることの多すぎる子育て家庭ではほんまに使えます。
「やれたらやること」はあくまで努力目標
休養の本質的な項目である「やること」に対し、「やれたらやること」は休養や生活の質を上げるための努力目標です。
「やること」だけをする生活を続けるうちに「やれたらやること」にも時々スタンプが押せるようになります。
- ボーっとする
- 朝の日光を浴びる
- ストレッチ
- 散歩(5分)
- 風呂
- 洗濯
- 掃除
ただし、「やれたらやること」は、「やること」よりも活動量が多いので無理はしません。私の場合はちょっとやってみようと思ったときにやってみて、少しでもしんどいと感じたら途中で切り上げることも多かったです。やらないでいると不快感がつのったり、体質によって健康に差しつかえたりもするので、そのへんは体調と相談しましょう。
私はお風呂をサボりすぎて痒くなったりしたので、2~3日に一回覚悟を決めてお風呂に浸かるようなレベルでした……
「やれたらやること」がほとんど埋まるようになった頃、以前と比べて少し元気になっていることを自覚しました。「やれたらやること」が全部埋まるまでには月単位の時間がかかり、体調によって逆戻りすることもあるので、埋まらないことに焦る必要は全然ないと思います。
適切に子どもと関わるために必要なものは育児書ではなく休養
私は育児書を読むのが大好きで読み漁っています。
育児書は、子どもとの関係に悩む親に向けて「自己肯定感を育てる」とか「接し方や言葉がけを変えてみる」と書いてあることが多いですが、親自身が疲れ切っているときに育児書が進める関わり方をするのは困難です。表面を取り繕うことはできても、無意識レベルの表情やしぐさで肯定や受容とは真逆のメッセージを送っていることがあるので。
以下はすべて私のやらかしですが、
- 子どもの「みて~」に対して、ろくに見もせずにほめる
- 口先ではほめても、声に乗っている感情が「めんどくさい」
- 子どもの「だっこ~」に対して、だっこはするけどおざなり
- 子どもをあまり見ずに他のことを考えて上の空
親の方は大したことだと考えず見過ごしがちですが、子どもは敏感に察して傷ついたりします。
うちの娘の場合の話ですが、娘は生まれた時からたいへん癇の強い赤ん坊でした。イヤイヤ期を経て3歳を過ぎると更にパワフルになり、瞬間湯沸かし器どころか粉塵爆発みたいな癇癪を起こすことがあります。そして、癇癪は私が疲れているときや睡眠不足のときに集中することが多いです。
私の方は「どうしていつも私が疲れているタイミング?何か恨みでも?」と思って子育てが嫌になりかけていましたが、私の二枚舌を察した娘が混乱して癇癪を起こしていると考えれば辻褄が合います。
長期間にわたって二枚舌で接すると、本来は最も身近で最も信頼できるはずの大人を信頼できなくなりかねません。世界に対する信頼感は人生のごく早期に主に養育を担う親との関わりを通じて育まれるものなのに、それすら信頼できない子どもはいったいどうやってこの世界を信頼して安心して生きていくことができるのかという話に発展しかねません。
いわゆる「毒親問題」というやつですが、先々を考えても親の休養は大切だと思います。
ちなみに私がよく眠っていて元気な時は、娘はあまり癇癪を起こしません。テレビやジュースなどの要求が通らなかったときに一瞬「ギャー!」となるくらいですかね。娘は抱っこ魔なので二言目には「だっこ!」と言うし、家事をしているときに時々「みて~」「よんで~」はありますが、求める通りに応えればすぐにお腹いっぱいになる様子です。
子どものお世話も本当に弱っているときのやることリスト準拠で案外大丈夫
子育て中の親が休養に専念することは難しいところもありますが、疲れや睡眠不足で床にへたりこんでしまうようなときや、子どもとの関係がなんだかしっくりこないときは、やはり「休養以外のことはしない」日が少しは必要です。
だから、そういう日くらいは子どものお世話も生存に必要なレベルに絞ってもいいと思うんですよね。子どもに持病がなければそれこそ「食べさせる/寝かす/排泄物を始末する」レベルでも何とかなります。
- 「今日はアンパンマンカレーと野菜ジュース」でも、時々なら子どもはむしろ喜ぶ
- お風呂をサボると子どもの頭が臭くなるかもしれないけど、臭くなったら洗えばいい
- 片付けをサボると部屋の中は大惨事だけど、元気になったら片付けたらいい
- 洗濯をサボって服が足りなくなったら、嗅いでみて大丈夫そうなら着たらいい
育児や家事の最低ラインはこのあたりまで下ろしても意外と大丈夫なことを知っていれば、自責の念が和らいで気分だけでも楽になりますし、それで少し笑える元気が出たらまたやり直したらいいと思います。本当にのんびりいきましょう。
子どもが大人になるまでは本当に長いです。子育ては短期決戦ではなく長期戦なので、無理は絶対にしないことが大切です。
てなわけで私も少し寝ます。それではおやすみなさいませ!
実際問題、子どもが放っておいてくれないせいで休養できないことがあり、こればっかりはどうしたもんかねと思っています。もはや抱っこして寝るかな(笑)